| 1月の園だより |
|
あけましておめでとうございます。今年も昨年に引き続き、宜しくお願いいたします。
本園では、毎月16日に「しんらんさまの日」という行事を行っています。これは浄土真宗を開かれた親鸞聖人の祥月のご命日が1月16日であることから、月命日の法要を行っているのですが、その中で毎月「保育主題」をもとに、子どもたちに話をしています。その中で、いろいろなことを子どもたちに教えているのですが、お参りの中の法話だけでなく、年間を通して個別でも子どもたちに語り掛けていることがあります。
それは「自分が言われたり、されたりしたくないことは、他の人にしてはいけない」ということです。これは私たちが社会生活を行う中で基本的な事柄だと言えますが、私自身が前園長・理事長である亡き父から、「己の欲せざるところ人に施すことなかれ」と、原文のまま子どもの頃に繰り返し言われ続けた言葉です。この言葉は『論語』の中で、孔子とその弟子である子貢との問答の中で述べられたものですが、意訳すると概ね次のようになります。
孔子の弟子の子貢が「先生、一言で生涯を貫きとおす言葉はありますか」と尋ねました。
すると孔子は「それは恕(思いやりの心)ではないか。自分が言われたりしてほしくないことは、他人にもしてはならない」と答えました。
園の中では、毎日のように「友達にたたかれた・噛まれた」とか、「嫌なことを言われた」といった子ども同士のトラブルが発生します。そのようなことが起きた場合、対処の仕方は当事者の年齢や月齢にもよりますが、コミュニケーションが可能な子どもの場合は、「自分がたたかれたり噛まれたり、あるいは嫌なことを言われたりしたらどうか」ということを問いかけます。
すると、ほとんどの子から「嫌だ!」という答えが返ってきます。そこで「では、自分は友達にたたかれたり噛まれたり、悲しくなるようなことを言われたれするのが嫌なのに、どうして友達にそのようなことをするのか」と重ねて問うと、みんな返事に窮してしまいます。
そして、しばらく沈黙が続いた後、いつも「自分が言われたり、されたりしたくないことは、他の人に言ったりしたりしてはいけない」ということを語り掛けます。子どもなりに、たたいたり噛んだりすることはいけないことだと理解することはできるようですが、ついかっとなって衝動的にたたいたり噛んだりするようです。
その一方、言葉の面では一応理解はしていても、なかなか実践できない子が少なからずいたりします。テレビゲームやアニメ、YouTubeなどの影響なのか、友達に「死ね!」とか「ぶっ殺す」といった言葉を口にしたりする子がいたりします。
そのような子には、「自分の言われたくないことは友達に言ってはいけない」ことを教え、口は一つしかないのだから、せっかくのことなら悲しくなるようなことを口にするのではなく、友達が笑顔になるようなことを言うように話しています。
たとえ一回で理解・実践することはできなくても、私が子どもの頃に繰り返し言われたことを今でも覚えているように、子どもたちの心の中に「恕」という言葉で語られた「他を思いやる心」が生涯を通して貫かれることを願っています。
|
 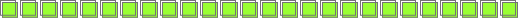 |
| クラスだより |
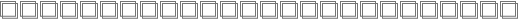 |
| さ く ら 組 |
|
今月前半は、凧あげやこま遊び、すごろく、かるた遊びなど、お正月ならではの遊びを楽しみたいと考えています。昔ながらの遊びを通して、最近は希薄になってきたお正月気分を味わってほしいなと思っています。
凧は、先月それぞれ好きな絵を描いて仕上げたので、もも組・うめ組と一緒に中央公園の広場に行って、凧あげを行うことにしています。
こまも先月、自分の好きな色を塗ったり、模様を描いたりしてオリジナルのコマを作ったので、『(指先だけで回す)ひねりごま』や『(紐を使って回す)投げごま』に挑戦します。どうすればこまがよく回るのか一緒に考え、工夫しながら遊びに興じたいと思っています。
かるた遊びは、これまで「アンパンマンかるた」などをしたことがあるので、遊び方は知っているのですが、今回は単に遊ぶだけでなく「なぞなぞかるた」や「漢字かるた」などを使って、グループで競い合いながら楽しむ形式で行いたいと思っています。かるたは読み手の言葉を聞いてカードを取るという遊び方が一般的ですが、なぞなぞを解いたり漢字の札を探したりすることで、「聞いて→取る」の間に「考える」という作業が一つ入るので、遊びを通して楽しみながら考える力をつけたりすることが期待されます。また、自分の名前を漢字で書ける子もいたりするので、一層漢字に興味を持ってほしいと思います。
7日は、願生寺の本堂で七草式があります。今回さくら組は1月~3月生まれの子どもたちが対象になりますが、4月~12月生まれでもご希望があれば名前を読み上げます。また、当日の給食には「七草粥」が出されます。「春の七草(せり・なずな・ごぎょう・はこべら・すずな・すずしろ・ほとけのざ)」を教えたり、七草式とはここまで無事に成長できたことをみんなで喜び合うと共に、周囲の人々の恩恵に感謝する機会であることを理解できるようにしたいと考えています。
今月後半は、16日に「報恩講」の行事があります。報恩講では、毎年お参り・法話の後に、もも組・うめ組と一緒に「おにぎり作り」をしています。自分でおにぎりを作ることで、おにぎりは一粒一粒のお米が集まってできていることに気付き、同じように自分のいのちも多くのいのちに生かされて生きているということを理解してもらいたいです。また、おにぎり作りを通して日頃何気なく口にしている多くのいのちや、いろいろな人たちの恩恵に感謝したりする機会にしたいです。さくら組はたくさん食べる子が多いので、楽しみながら作りいっぱい食べてほしいです。
設定保育では、縄跳び、ルールのある遊び、お店屋さんごっこの話し合いなどを計画しています。
縄跳びは、習熟度に個人差があるので、1回跳びから連続で跳べるように練習を続けていきたいです。また、長縄を使った遊びも取り入れたいと思っています。
ルールのある遊びでは、子どもたちのリクエストに応えて「ドッジボール」を予定しています。遊び方の説明をよく聞き、遊びを通してルールを守る大切さを学んでほしいです。
2月に「お店屋さんごっこ」を予定しています。そこで、先ずはどのようなお店屋さんを出店するかを話し合うことから始めようと思っています。さくら組では、定期的に廃材遊びを行っているのですが、どんどんクオリティが上がってきているので、どんな商品を作るのかも、子どもたちと話し合って決めていくことにしたいです。
|
|
| も も 組 |
|
今月前半は、お正月遊びの「凧揚げ」や「かるた遊び」「福笑い」などを予定しています。
凧揚げは、先月下旬に自分で好きな絵を描いてオリジナルの凧を作ったので、園外保育に行く時に持って行って、中央公園の広場で揚げることにしています。
かるた遊びでは、「ことばあそびかるた」や「アンパンマンビッグかるた」を使って楽しみたいと思っています。文字を読むことに興味を持ち始めている子が増えてきているので、平仮名を読める子には、文字札を読む役割を交代でしてもらうことにしています。福笑いでは、それぞれどんな顔ができあがるのか、とても楽しみです。昔ながらのお正月遊びを楽しむことを通して、お正月気分を味わってもらいたいです。
また、休み明けは、子どもたちが冬休みの間にそれぞれ経験したことに耳を傾け、みんなで休みの間の楽しかったことなどを語り合いたいと思っています。
7日の午前中に願生寺の本堂で「七草式」があります。今回もも組は、4月から12月生まれの子どもたちが対象になります。本堂では、受式する園児一人ひとりの名前を阿弥陀さまに奉告すると共に、ここまで無事に生育できたことをみんなで喜び合ったり記念撮影をしたりします。
当日の給食には行事食として「七草粥」が出されます。この機会に「春の七草(せり・なずな・ごぎょう・はこべら・すずな・すずしろ・ほとけのざ)」の名前を覚えてもらいたいです。また、七草を食べることにはどんな意味があるのか事前に教えて、興味を持って食べられるようにしたいです。
16日には「報恩講」の行事があります。報恩講では、仏参、法話の後に毎年「おにぎり作り」をしています。いつもあまり意識することもなく口にしているお米ですが、当日は事前にお米が出来るまでの過程を説明し、一粒一粒のお米が自分たちの口に入るまでには自然の恩恵や心を込めて育ててくださった農家の方々のご苦労など、たとえ直接目にすることは出来なくても、そこに命を支える多くの働きがあることを伝えていきたいです。また、手洗い・うがいの必要性についても話し、衛生観念が定着するように留意しながら進めていきたいと考えています。
21日は、さくら組と一緒に、リナシティのプラネタリウムに冬の星座鑑賞に行きます。これまで季節ごとに鑑賞に行っているのですが、春・夏・秋の星座を観た時と同じように、今回も前もって冬の夜空にはどのような星座が見られるのかを図鑑でよく調べてから行くことにしています。
設定保育では、文字や数字のテキストを使った学習や文字スタンプ遊び、戸外遊び、切り紙遊びなどを予定しています。
文字スタンプ遊びは、4月から平仮名の読み書きの学習を継続的に行っているのですが、月齢差などの関係から子どもによって習熟度に差があるので、スタンプ遊びを通して楽しみながら文字の読み方を覚えられるようにしたいです。
戸外遊びは、外の空気や土に触れることで、さまざまな微生物やアレルギー源と接触し、これが体内の免疫機構を刺激し、病気やアレルギーに対する抵抗力を高めることが期待できます。いろんなバーションの鬼ごっこやドッチボールなどのルールのある遊びを楽しんだりして、風邪に負けない体作りをしたいと思っています。
切り紙遊びでは、折り紙を使い、簡単な繋がる切り絵に挑戦する予定です。
|
| う め 組 |
|
今月前半は「凧揚げ」「こま遊び」「かるた遊び」「羽根つき」など、お正月ならではの遊びを予定しています。
「凧揚げ」は園外保育の際に中央公園に持って行って、さくら組・もも組の子どもたちと一緒にあげて遊ぶことにしています。先月オリジナルの凧を制作した際、この凧をもって中央公園に凧揚げに行くことを話すと、みんなとても楽しみにしているようでした。中央公園で凧揚げをするのは初めてなので、持ち方・飛ばし方などをよく教えた上で臨みたいです。
「こま遊び」は、こちらも先月オリジナルのコマを制作しているので、それを使って遊びたいと思います。こまは奈良時代に中国から日本に伝わった伝承遊びで「物事が円滑に回る」という意味からお正月の遊びとしても親しまれてきました。今回うめ組は、紐を使って回す「投げごま」ではなく、指先を使ってこまの心棒を回す「ひねりごま」で遊びます。こま遊びは、指先や腕のコントロール、目と手の協調性や、「どうすれば上手く回るか」と考えて試すことで思考力を養ったりすることが期待できます。根気強く挑戦して、うまく回せるように声掛けしていきたいです。
「かるた遊び」も、先月に引き続き実施していく予定です。数名、少しずつ平仮名の読みを覚えてきている子もいるので、さらに関心を深められるような遊び方も取り入れていきたいです。
「羽根つき」は、羽根を風船に置き換えて画用紙で作った羽子板で遊びたいと考えています。羽付きは、動く羽根の位置を視覚で確認し、手と足を動かして羽根を打つ動作が必要になります。また、羽根が移動するであろう位置を予想しバランスよく体を動かす運動能力も必要です。追い羽根と風船とではだいぶ動きや速さが違いますが、子どもたちにとっては風船がちょうど大人にとっての追い羽根の動きに匹敵するのではないかと思われます。先ずは、保育者が飛ばした羽根を上手く打ち返せるようにするところから始めたいと思っています。
今月後半は、「報恩講」の行事があり、その中で「おにぎり作り」があります。報恩講では、ただ単に「おにぎりを作って食べた」と言うことだけに終わるのではなく、事前にお米が出来るまでの過程や、おにぎりは一粒一粒のお米が集まって形作られていることなどを話し、いつも食事ができるのは決して当たり前ではないということに気付いて欲しいです。また、自分で握るおにぎりの味は格別だと思います。その美味しさを味わうことで、食べることへの喜びや食材を作ってくれた人、調理をしてくれた人たちへの感謝の気持ちを育んでいきたいです。
他にも、「伝承遊び」や「星座鑑賞」「テキスト学習」などを予定しています。
「伝承遊び」では、「はないちもんめ」を楽しみたいと思っています。ルールをしっかりと説明したうえで仲良く遊べるように配慮していきたいです。
「星座鑑賞」では、遊戯室でプロジェクターを使って冬の星座を鑑賞する予定です。「夜お星さま見た!」とか「なんで朝なのにお月様あるの?」とか空の様子に興味を持っている子も増えてきているので、冬の夜空に浮かぶ星座を鑑賞し、より関心を深めていきたいです。
「テキスト学習」では、「たのしいかず」や「はじめてのせん」などのテキストを使って、数字について学んだり、線を引く練習などを予定しています。
|
| す み れ 組 |
|
子どもたちの元気な挨拶の声と共に、新しい年がスタートしたことと思います。早いもので、今年度も残すところ3か月程になりました。すみれ組での毎日が充実したものとなるよう、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。
今月は、子どもたちが園では一番長い休みとなる冬休みの間、それぞれどのようにして過ごしていたのか、語りかけに耳を傾けることから始めていきたいです。
今月の保育は、お正月にちなんだ遊びを取り入れることにしています。
かるた遊びでは、まだ文字を読めないので、子どもたちの大好きなアンパンマンの大型かるたを使うことで、遊びを通して文字への興味を高めたいと考えています。かるたは、すみれ組の子どもたちにとって初めての経験する遊びなので、丁寧にルールを説明し、保育者も加わって一緒に遊ぶことにしています。札を取る際、今回は文字ではなく絵を見て判断することになりますが、様々なかるたの絵札を比較し、違いを見つけて絵札を取るという経験を通して「見分ける力=判断力」や俊敏性などを身につけてもらいたいです。
制作では、お正月ならではの遊び“福笑い”を題材に取り上げます。また、福笑いの顔には、今年の干支にちなんで馬の顔を考えています。「笑う門には福来る」ということわざがあります。これは「笑いの絶えない家には自然と幸福が訪れる」という意味ですが、その語源になったのが“福笑い”だという説があります。福笑いでは、目をつぶったり目隠しをしたりして、形や大きさなどの感触を頼りにどこのパーツなのか見当をつけていくため、子どもたちの想像力が刺激されます。福笑いをする子と見る子に分かれて、全員で楽しみながら、たくさん笑いたいと思います。
この他、昔ながらのお正月遊びの中から、こまを題材に取り上げた制作も行う予定です。お昼寝前の絵本の読み聞かせの中で、こまの作り方を紹介すると、ほとんどの子が「こまだ!」と言って大喜びでした。そこで「こま作ってみる?」と尋ねると、「つくりたい!」という答えが返ってきたので、オリジナルのこまを作り、保育室でして楽しみたいと思います。
こま遊びには、たくさんのねらいがありますが、その中の1つに手首や指先を細かく使う「微細運動」があります。最近、お箸で食べる子が増えてきていますが、お箸へ移行中の子はスプーンを下から持ったり、お箸のように持ったりして食べています。まだ、手首や指先がうまく使えずに、給食をこぼしてしまったりすることがあるので、こまで楽しく遊びながら「微細運動」を行うことを通して、お箸へのスムーズな移行につなげていければと思っています。
現在、登園後の支度や給食の後片付け、帰りの支度など、自分の身の回りのことを自分でするように声掛けしています。子どもたちは楽しそうに取り組んでいるので、出来た時や頑張っている姿を十分に認め、「自分で出来る!」という喜びや自信に繋げ、自分で出来ることを少しずつ増やしていきたいです。
また、「当番活動」も取り入れることにしています。当番活動には、「自己肯定感が育まれる」「責任感が培われる」「自分で考える力や生活スキルが身につく」といった事柄が期待されます。お手伝いは、子どもにとっては楽しい遊びの一つでもあるので、当番活動を通していろんなことを身につけてほしいです。
|
| も み じ 組 |
|
今月前半は、冬休み期間の出来事を語り合うことから始めたいと思っています。
年度当初は、わずかな単語しか口にできない子が多かったのですが、最近数名の子が「海行ったよ」とか「ママと買い物行った」などと、二語文~三語文で語りかけてくるようになってきました。
月齢の高い子どもたちは、記憶力の方もだいぶ増してきているようで、前日あったことを楽しそうに話してくれることがあります。園では、年末年始の休みが一番長い休みの期間(例年は6日間)になるのですが、今回はちょうど日曜日と日曜日の間に挟まったこともあり、最長の8日間になりました。この休みの期間に、子どもたちがどのようなことを体験したのか聞かせてもらうのが、とても楽しみです。
まだうまく話せない子は、自分の思っていることを身振りや手振りを交えながら伝えようとしてくれるので、仕草や言葉から伝えたいことの意図をくみとり、それを「○○したんだね」などと言い表して確かめることで、コミュニケーション能力を高めていきたいです。そのためにも子どもたちの語り掛けには、それぞれ丁寧に耳を傾けたり応じたりするようにしていきたいです。
また、お正月に関する絵や写真が載っている絵本があるので、読み聞かせを通してお正月ならではの行事や遊びを教えたり一緒に楽しんだりしたいと思っています。そこで、制作では昔ながらのお正月遊びの中から「凧」と「こま」を題材に取り上げる予定です。
凧作りでは、ビニール袋で作った凧に絵を描いたり、シールを貼ったりしてそれぞれオリジナルの凧を作ることにしています。また、天気のいい日には園庭に出て凧あげを楽しみたいと思います。
こま作りは、牛乳パックや紙コップなど、身近な廃材を使って作りたいと考えています。凧同様にシールなどを使ってオリジナルな物を作り、保育者も子どもたちと一緒にどうしたらよく回るか考えたりしながら、一緒に楽しめたらいいなと思っています。
今月後半は、リトミック・粘土遊び・園庭遊びなどを予定しています。
リトミックは、音楽を通じて表現力や感性を養う教育方法のひとつで、具体的な取り組みは以下の通りです。
・リズム運動:一定音にあわせて身体を動かし、知的能力を培う
・ソルフェージュ:メロディーを聞いて楽譜を読むまたは歌をうたい、音程を確認する
・即興演奏:音楽を即興で演奏する
乳幼児期は、子どもたちが音楽の楽しさに触れられるようにするため、主にリズム運動が取り入れられています。リトミックでは、耳で音を聴き、それを反射的に理解して表現することが必要となりますが、これは耳が良くないと判断することができませんし、音や曲に集中していないと即座に反応することもできません。定期的にリトミックを取り入れていくことで、楽しみながら判断力や表現力、集中力などが少しずつ身につくようにしていきたいです。
園庭遊びでは、子どもたちは4月当初のたどたどしい動きからすると、だいぶ運動能力が高まり、走りまわったり転がったり飛んだり跳ねたりするなど、器用に身体を動かせるようになってきたので、園庭遊びの機会を増やし、寒さに負けない身体作りをおこなっていきたいと思います。
|
| つ ぼ み 組 |
|
月齢6か月の子どもは、目の前のおもちゃやプレイジムに手を伸ばして「ガチャガチャ♪」と音を鳴らして楽しむようになったり、「○○ちゃん」と声をかけると保育者の声のする方に振り向いて「あーうー」と声を出し、笑顔で応えたりするようになってきました。
また、空腹だったりオムツが濡れたり構って欲しかったりするような時は、そのことを泣いて知らせるようになってきました。そのような時は、すぐミルクを飲ませたりオムツを変えたり抱っこしたりして、生理的な欲求を十分に満たすようにして、快適な環境の中で安心して園での一日を過ごせるように努めています。
1歳になった子どもたちは、言葉でのコミュニケーションが盛んになり、保育者と一緒に見立て遊びやつもり遊びを楽しめるようになってきました。
そこで、ままごと遊びやぬいぐるみ遊びなどを通して、「どうぞ」「ありがとう」「いただきます」「ごちそうさま」といった簡単な言葉のやりとりを楽しんだりして、少しずつ口にできる言葉の数が増えるようにしていきたいと思っています。
また、最近はだんだん「自分でしたい!」という気持ちが芽生えてきて、保育者が「○○しよう」と声をかけると、「いや!」と言った感じで首を振ったり、保育者の手を払いのけて逃げたり、部屋の隅に行って隠れたり、時には泣き出したりするようになってきました。
この時期は「いやいや期」とも呼ばれ、子どもに自我が芽生え何でも自分でしたがるようになる一方、うまく出来なかったりすると、すぐに泣いたりかんしゃくを起こしたりするなど、なかなか対応の仕方が難しかったりします。
また、自分の思っていることをうまく言葉にして伝えられない上に、それを相手が理解してくれないことへのいら立ちから発せられる自己表現なので、子どもの気持ちを尊重し、「いや」という意思表示を無視したりせず、何を伝えようとしているのか言葉にして確かめ、出来るだけ子どもの思いに寄り添うことに努めたり、健やかな成長を見守ったりしていきたいです。
友達との関わり方においては、これもまだ言葉による意思疎通が十分に出来ないことから生じることなのですが、自分の欲しいおもちゃを他の子が使っている時など、「貸してほしい」ということをうまく伝えられず、とっさに叩いたり噛みついたりしてしまうことがあります。
まだ「たたく・噛みつく」=「悪いこと」という認識がなかったりするので、衝動的にたたいたり噛みついたりしてしまうので、子どもの気持ちを代弁したり、叩いたり噛んだりするのは「いけないことだ」ということを少しずつ理解できるよう語りかけていきたいです。
食事面では、自分で食べたりコップで飲んだりする練習をしています。まだ、こぼしてしまうことがよくありますが、「自分でする!」という意欲的な態度の見られる子が多いので、すぐに援助したりせず、自分でしたがっているときはできるだけ自分でさせるようにして、上手に食べたり飲んだりすることが出来たときは、褒めたり一緒に喜んだりしながら成長を見守っていきたいです。
保育では、溶けない雪・粘土・スライムなどを使った感触遊びや、制作ではお正月遊びの中から「凧」を題材に取り上げることにしています。
今月は、年間を通して一番寒い時季になりますが、天気の良い暖かい日には園庭に出て、凧あげをしたいと思っています。
|
| 給 食 だ よ り |
|
今月の7日は、七草粥を作ります。昔から正月7日は「人日の節句(じんじつのせっく)の日」として、七日正月とも呼ばれており、多くの家庭で七草粥が食べられてきました。
七草粥を食べることには、主に2つの理由があります。それは、無病息災と長寿健康です。
無病息災とは、病気をしないこと、何事も達者なことを意味する言葉で、他にも災害や病気などの災いを防ぐという意味をもっています。また、健康長寿とは、いつまでも健康で長生きするという意味の言葉です。
江戸時代は、現在よりも寿命はずっと短く、どうすれば健康でいられるか、長生きするための生活とは何かなど、今よりも色々なことが分かっていない時代でした。その中でも「健康でありたい、長生きしたい」という意味を込めて七草粥を食べたということは、それだけ当時の日本人にとって「体に優しい」「健康的」な食事と捉えられていたからだと思われます。
7日は「松の内(1月1日~1月7日)」の最後の日になりますが、お正月のごちそうに疲れた胃腸をいたわり、青菜の不足しがちな冬場の栄養補給をする効用もあることから、この日に七草粥を食べることで新年の無病息災と長寿健康を願うようになりました。
春の七草は、「せり:水辺の山菜で香りが良く食欲が増進する」「なずな:別称はペンペン草。江戸時代にはポピュラーな食材」「ごぎょう:別称は母子草で草もちの元祖。風邪予防や解熱効果」「はこべら:目に良いビタミンAが豊富で、腹痛の薬」「ほとけのざ:別称タビラコ。タンポポに似ていて食物繊維が豊富」「すずな:かぶのこと。ビタミンが豊富」「すずしろ:大根のこと。消化を助け風邪予防効果」などで、それぞれに付記しているような特長があります。園では、七草の他に、人参・鶏もも肉も使用し、かつおだしと薄口醤油、味醂で味付けをして作ります。七草粥や毎日の給食をたくさん食べて、今年も元気に過ごしてほしいです。
その他の給食には「魚の照り焼き」「ちくわの磯辺揚げ」「ミートボール」がある他、おやつには「白玉ぜんざい」「大豆の甘辛揚げ」「ココアちんすこう」などがあります。
 
|
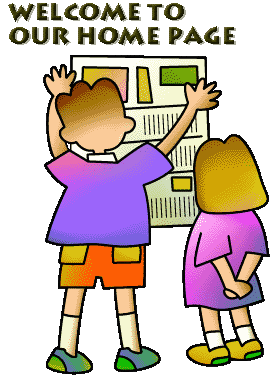









![]()